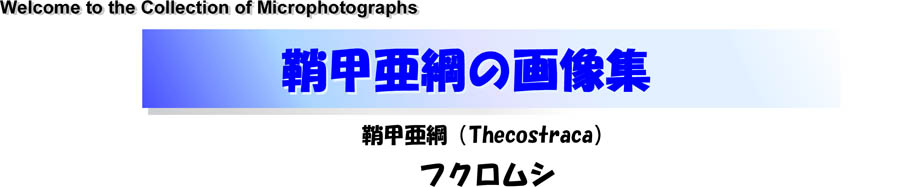鞘甲亜綱_キプリス幼生_8a
採取:福島県いわき市(2022年7月) *海岸
撮影:深度合成画像。
殻長:0.5mm
特徴:夜間ネットサンプリングで採取。
8a
7b
鞘甲亜綱_ノープリウス幼生_7a,b
採取:神奈川県城ヶ島(2021年11月)
撮影:深度合成画像 殻の長径:0.79mm 特徴:夜間ネットサンプリングで採取。
7a
--------------------------------------------------------------------------------------
参考文献:(1)節足動物の多様性と系統 (バイオディバーシティ・シリーズ 6)
石川良輔編、岩槻邦男・馬渡峻輔監修、裳華房、2008年、p227-234.
--------------------------------------------------------------------------------------
ノープリウス幼生(nauplius larva)
キプリス幼生(Cypirs larva)
3mm
1cm
4b
4a
5mm
5mm
6b
6a
フクロムシに寄生されたイワガニ_6a,b
採取:神奈川県藤沢市 江ノ島 (2019年7月)*海岸
特徴:腹部の黄色い部分がフクロムシのエキステルナ。
フクロムシに寄生されたイワガニは健全な個体よりも動きが鈍かった。
←蔓脚
←蔓脚
2mm
2mm
2mm
2mm
1d
1c
1b
1a
3mm
柄部
頭状部
カメノテ(Capitulum mitella)_2a
採取:神奈川県葉山町(2014年8月)*海岸
撮影倍率:x0.67(実体顕微鏡)
体長:16.8mm
特徴:小型のカメノテ。
三浦半島西岸では3cmを超えるようなカメノテは見つからない。
カメノテの体は大きく、頭状部と柄部に分けられる。
頭状部の上部には爪のような殻板が8枚ある。
頭状部の下部は、20以上の殻(付随小殻板)で覆われている。
柄部は、うろこ状の構造(柄鱗)に覆われている。
2a
カメノテ
口器→
エボシガイ(Lepas anatifera)_3a〜c
採取:東京都伊豆大島 (2018年3月)*海岸
全長:11.6mm
頭状部:6.6mm
特徴:発泡スチロールに付着していた個体。口器が殻の外に露出している。
写真2bと2cは蔓脚を暗視野で観察した画像。
3c
3b
3a
2mm
2mm
エボシガイ
フジツボ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鞘甲亜綱というと聞きなれない感じがしますが、フジツボ、エボシガイ、カメノテの仲間(蔓脚下綱)です。
この仲間の多くは、海岸などで固着生活を営んでいます。カニなどに寄生するフクロムシ(蔓脚下綱 根頭上目)も
鞘甲亜綱のなかまです。フジツボやフクロムシの成体は、とても甲殻類とは思えない外見ですが、ノープリウス幼生を
持つことから甲殻類であると分かります。鞘甲亜綱では、ノープリウス幼生の次にキプリス幼生に変態します。
キプリス幼生はカイミジンコに似た形態をしています。フジツボの場合はキプリス幼生の次に固着生活に移りますが、
フクロムシでは、さらに複雑な変態をします。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
フクロムシ
Since 2005/9 Copyright 2023 Neko no Shippo
フジツボ(フジツボ亜目:Balanomorpha)_分類群01_1a〜d
採取:宮城県石巻市(2017年8月)*海岸
撮影倍率:x0.67(実体顕微鏡)
長径:14.1mm、殻高:12.2mm
特徴:木製の杭に付着していたものを採取した。写真1bと1dは蔓脚を出している状態。
殻は山の斜面に当たる峰板、峰側板、側板、嘴板と、山頂部の背板、楯板からできている。
カルエボシ(Lepas anserifera)_5a〜e
採取:東京都伊豆大島 (2018年3月)*海岸
全長:9.8mm
頭状部:6.4mm
特徴:写真4aと4bは同じ個体。裏表、両側から観察した。
写真4c〜4eは殻の表面の拡大像。殻面に放射状の模様があることからカルエボシと同定した。
5b
5a
2mm
2mm