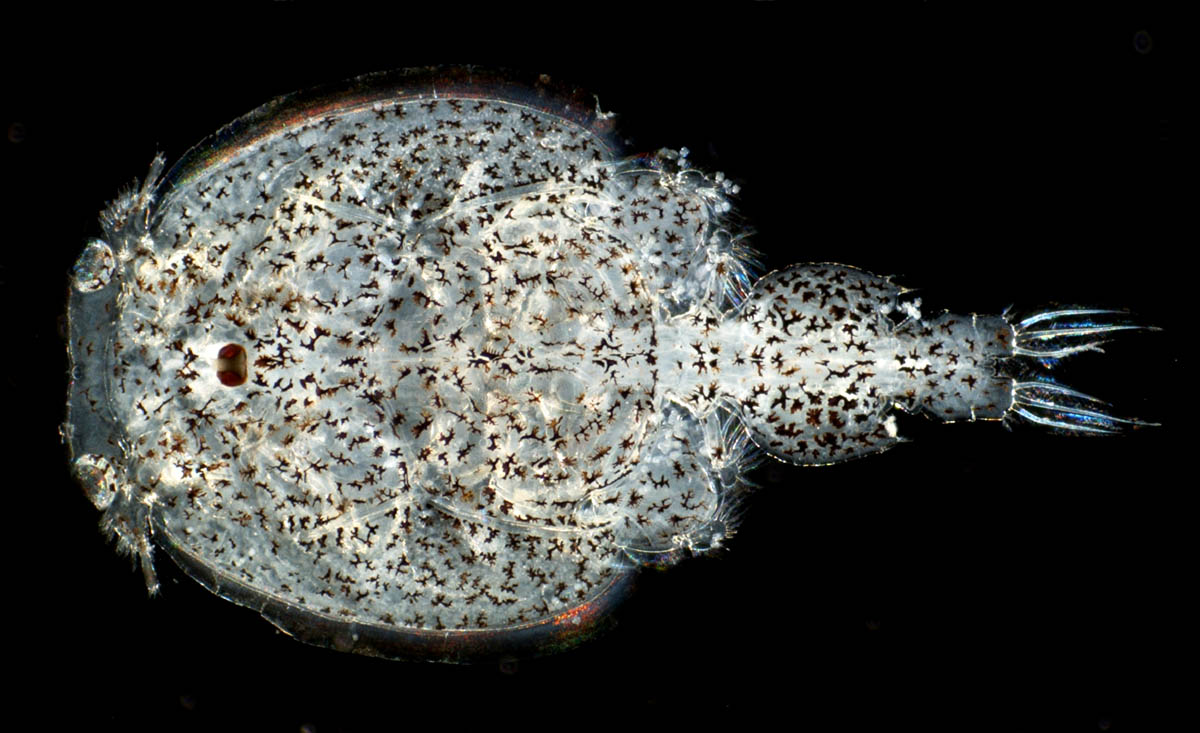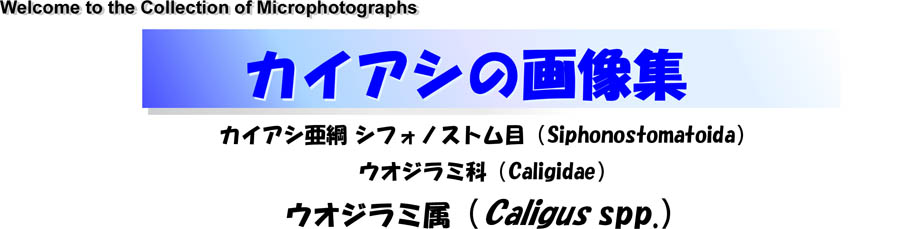1a
1mm
1c
200μm
1b
200μm
1d
100μm
ウオジラミ(Caligus orientalis)_1b~d
撮影倍率:x100(生物顕微鏡)
特徴:写真1bと1cはウオジラミの先端部分。
写真1bは背面側、1cは腹面側。
前縁部の目のように見える構造は吸盤(lunules)。
写真1dは目の拡大画像。目は背面にある。
ウオジラミの体の名称については、Nobnob氏による
“Nob!!の勝手に甲殻類”中の記事“続・ウオジラミ”を参考にした。
ウオジラミ(Caligus undulatus)_3r~u
撮影倍率:: x100(生物顕微鏡)
特徴:腹面から見た各部位の拡大画像。写真3rと3sは顎脚と思われる。
200μm
200μm
200μm
200μm
3u
3t
3s
3r
ウオジラミ(Caligus undulatus)_3o~q
撮影倍率:x100(生物顕微鏡)
特徴:ウオジラミの先端部分の拡大画像。写真3oは目の拡大画像。
写真3pと3qの前縁部の目のように見える構造は吸盤(lunules)。
ウオジラミの体の名称については、Nobnob氏による
“Nob!!の勝手に甲殻類”中の記事“続・ウオジラミ”を参考にした。
200μm
200μm
200μm
3q
3p
3o
Since 2005/9 Copyright 2023 Neko no Shippo
ウオジラミ(Caligus orientalis)_1a
採取:東京都 お台場(2017年9月)*海岸、夜間
撮影倍率:深度合成画像
体長:4.3mm(*触覚含まない、枝状肢含む)
前体部:2.6mm
特徴:背面から観察した画像。
お台場で夜間のプランクトンネット採取で見つけた。
鷲宮ほうき様に下記コメントを頂きました。
“生殖節後縁の棘からCaligus orientalisっぽい”
ウオジラミの幼生(コペポディット期)_6a,b
採取:神奈川県城ヶ島(2022年1月)*海岸、夜間
撮影倍率:深度合成画像
体長:1.1mm
特徴:写真6aは背面から観察した画像。
写真5bは腹面から見た画像。
鷲宮ほうき様に下記コメントを頂きました。
“フィラメントがないのは、コペポディット期です。
積極的に宿主に付着する上にステージ時間がとても短いので非常にレアです。
飼育実験でしか得られなかったステージのはずです。”
ウオジラミの幼生_5a,b
採取:千葉県銚子市(2022年5月)*海岸、夜間
撮影倍率:深度合成画像
体長:0.68mm
特徴:写真5aは背面から観察した画像。
写真5bは腹面から見た画像。
6a
5a
4a
ウオジラミの幼生_4a,b
採取:東京都 お台場(2017年9月)*海岸、夜間
撮影倍率:深度合成画像
体長:0.7mm
前体部:0.4mm
特徴:写真4aは背面から観察した画像。
写真4bは腹面から見た画像。
写真4aの白矢印は宿主に付着するための
フィラメントと思われる。
写真4bの黄色矢印は第2触角かもしれない。
↓
3c
3d
3c
3a
ウオジラミ(Caligus undulatus)_3a~d
採取:東京都 お台場(2017年9月)*海岸、夜間
撮影倍率:: x4(実体顕微鏡)
体長:3.9mm(*触覚含まない、枝状肢含む)
前体部:2.0mm
特徴:写真3aは背面から観察した画像。
写真3bは腹面から見た画像。
写真1、2の個体と同時に採取した。
Nobnob氏のブログ、“Nob!!の勝手に甲殻類 ~ミジンコからタカアシガニまで~”
の続・ウオジラミ のページで紹介されている
Caligus undulatus Shen & Li, 1959に形態が良く似ている。
500μm
500μm
2f
2e
ウオジラミ(Caligus orientalis)_2e,2f
撮影倍率:x40(生物顕微鏡)
特徴:腹面から見た前体部の拡大画像。
第2触角は鉤状に変形していて、これで宿主の組織を貫いて取り付くとのこと。
広島大学大学院による“竹原ステーション(水産実験所)”中のカイアシ類の体のつくりのページより引用。
↓第1胸脚
↑顎脚
↓第2小顎
↑第2触角
ウオジラミ(Caligus orientalis)_2a,b
採取:東京都 お台場(2017年9月)*海岸、夜間
撮影倍率:x3(実体顕微鏡)
体長:5.1mm(*触覚含まない、枝状肢含む)
前体部:3.1mm
特徴:写真2aは背面から観察した画像。写真2bは腹面から見た画像。
写真1の個体と同時に採取した。おそらく同種と思われる。
2a
500μm
500μm
1g
1h
1e
ウオジラミ(Caligus orientalis)_1g~i
撮影倍率:x40(生物顕微鏡)
特徴:後体部の拡大画像。
写真1g, hは腹面から見た画像。写真1iは背面から見た画像。
ウオジラミ(Caligus orientalis)_1e,f
撮影倍率:1e: x3(実体顕微鏡)、1fx40(生物顕微鏡)
特徴:腹面から見た画像。
腹面には第1,2触角、第1,2小顎、顎脚、第1~4胸脚がある。
1mm
500μm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ウオジラミ(Caligus spp.)は海水魚に寄生するカリグス科(Calididae)のカイアシです。
魚の体表に寄生して体表から粘液や血液を食べるので、大量に規制された場合には宿主の魚が弱ってしまいます。
このため、養殖業などの漁業者からは嫌われています。
ウオジラミ(Caligus spp.)はノープリウス幼生期、感染コペポディット期、カリムス期、成体の順に発育します。
カリムス期はカリグス類に特有の幼生で、頭部先端のフィラメントで宿主に付着しています。
ウオジラミ属(Caligus 属)に近縁のLepepophtheirus 属はカリムス期の後に前成体期があります。
金魚などの淡水魚に寄生する甲殻類(チョウ)も“ウオジラミ”の別名を持つので注意が必要です。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
6b
5b
4b
←
3b
2b
500μm
1i
1f