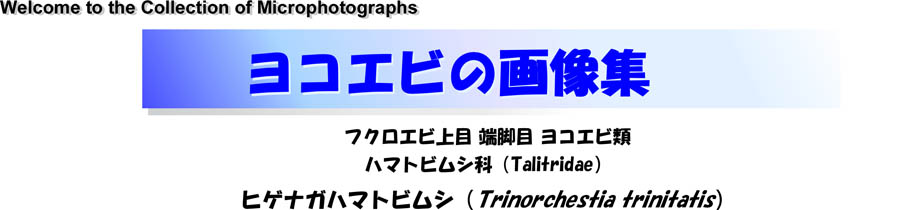ヒゲナガハマトビムシ(Trinorchestia trinitatis)_11a
採取:北海道石狩市(2016年9月)
撮影倍率:x0.67(実体顕微鏡)
体長:17.6mm
特徴:砂浜の海藻の下から採取した。
第2咬脚が小さいため、雌と思われる。
ヒゲナガハマトビムシ(Trinorchestia trinitatis)_10a
採取:北海道石狩市(2016年9月)
撮影倍率:x0.67(実体顕微鏡)
体長:17.7mm
特徴:砂浜の海藻の下から採取した。
第2咬脚が小さいため、雌と思われる。
ヒゲナガハマトビムシ(Trinorchestia trinitatis)_9a
採取:北海道石狩市(2016年9月)
撮影倍率:x0.67(実体顕微鏡)
体長:18.2mm
特徴:砂浜の海藻の下から採取した。
第2咬脚が小さいため、雌と思われる。
ヒゲナガハマトビムシ(Trinorchestia trinitatis)_8a
採取:北海道石狩市(2016年9月)
撮影倍率:x0.67(実体顕微鏡)
体長:18.6mm
特徴:砂浜の海藻の下から採取した。
第2咬脚が小さいため、雌と思われる。
ヒゲナガハマトビムシ(Trinorchestia trinitatis)_7a
採取:北海道石狩市(2016年9月)
撮影倍率:x0.67(実体顕微鏡)
体長:19.3mm
特徴:砂浜の海藻の下から採取した。
第2咬脚が小さいため、雌と思われる。
ヒゲナガハマトビムシ(Trinorchestia trinitatis)_6a
採取:北海道石狩市(2016年9月)
撮影倍率:x0.67(実体顕微鏡)
体長:21.2mm
特徴:砂浜の海藻の下から採取した。
第2咬脚が小さいため、雌と思われる。
ヒゲナガハマトビムシ(Trinorchestia trinitatis)_5a
採取:北海道石狩市(2016年9月)
撮影倍率:x0.67(実体顕微鏡)
体長:19.4mm
特徴:砂浜の海藻の下から採取した。
第2咬脚が小さいため、雌と思われる。
ヒゲナガハマトビムシ(Trinorchestia trinitatis)_4o
撮影倍率:x3(実体顕微鏡)
特徴:尾肢の画像。
ヒゲナガハマトビムシ(Trinorchestia trinitatis)_4n
撮影倍率:x4(実体顕微鏡)
特徴:第1腹肢の画像。
複数の節があるようにも見えるが、
合体して一枚の板のようにも見える。
日本海岸動物図鑑のホソハマトビムシの
腹肢のイラストよりもはるかに複雑。
ヒゲナガハマトビムシ(Trinorchestia trinitatis)_4m
撮影倍率:x2(実体顕微鏡)
特徴:第7胸脚の画像。
ヒゲナガハマトビムシ(Trinorchestia trinitatis)_4l
撮影倍率:x2(実体顕微鏡)
特徴:第6胸脚の画像。
ヒゲナガハマトビムシ(Trinorchestia trinitatis)_4k
撮影倍率:x2(実体顕微鏡)
特徴:第5胸脚の画像。
ヒゲナガハマトビムシ(Trinorchestia trinitatis)_4j
撮影倍率:x2(実体顕微鏡)
特徴:第4胸脚の画像。
ヒゲナガハマトビムシ(Trinorchestia trinitatis)_4i
撮影倍率:x3(実体顕微鏡)
特徴:第3胸脚の画像。
ヒゲナガハマトビムシ(Trinorchestia trinitatis)_4h
撮影倍率:x3(実体顕微鏡)
特徴:第2咬脚の画像。
第2咬脚の掌部は滑らか。
ヒゲナガハマトビムシ(Trinorchestia trinitatis)_4g
撮影倍率:x40(生物顕微鏡)
特徴:第1咬脚の拡大画像。
こぶ状の突起が2個ある。
ヒゲナガハマトビムシ(Trinorchestia trinitatis)_4f
撮影倍率:x3(実体顕微鏡)
特徴:第1咬脚の画像。
ヒゲナガハマトビムシ(Trinorchestia trinitatis)_4e
撮影倍率:x1(実体顕微鏡)
特徴:第2触角の拡大画像。
鞭部が柄部よりも長い。
ヒゲナガハマトビムシ(Trinorchestia trinitatis)_4d
撮影倍率:x40(生物顕微鏡)
特徴:第1触角の拡大画像。
ヒゲナガハマトビムシ(Trinorchestia trinitatis)_4c
撮影倍率:x40(生物顕微鏡)
特徴:顎脚の画像。
ヒゲナガハマトビムシ(Trinorchestia trinitatis)_4b
撮影倍率:x0.67(実体顕微鏡)
特徴:上から見た画像。
ヒゲナガハマトビムシ(Trinorchestia trinitatis)_4a
採取:北海道石狩市(2016年9月)
撮影倍率:x0.67(実体顕微鏡)
体長:19.7mm
第1触覚:1.8mm
第2触覚:10.2mm 柄部4.7mm 鞭部5.5mm
特徴:第2触角の鞭部が柄部よりも長いことが特徴。
雌は多数見つかったが、雄は比較的少数だった。
ヒゲナガハマトビムシ(Trinorchestia trinitatis)_3k
撮影倍率:x1(実体顕微鏡)
特徴:第7胸脚の画像。
ヒゲナガハマトビムシ(Trinorchestia trinitatis)_3j
撮影倍率:x1(実体顕微鏡)
特徴:第6胸脚の画像。
ヒゲナガハマトビムシ(Trinorchestia trinitatis)_3i
撮影倍率:x2(実体顕微鏡)
特徴:第5胸脚の画像。
ヒゲナガハマトビムシ(Trinorchestia trinitatis)_3h
撮影倍率:x2(実体顕微鏡)
特徴:第4胸脚の画像。
ヒゲナガハマトビムシ(Trinorchestia trinitatis)_3g
撮影倍率:x2(実体顕微鏡)
特徴:第3胸脚の画像。
ヒゲナガハマトビムシ(Trinorchestia trinitatis)_3f
撮影倍率:x2(実体顕微鏡)
特徴:第2咬脚の画像。
第2咬脚の掌部は滑らか。
ヒゲナガハマトビムシ(Trinorchestia trinitatis)_3e
撮影倍率:x40(生物顕微鏡)
特徴:第1咬脚の拡大画像。
こぶ状の突起が2個ある。
日本産土壌動物のヒゲナガハマトビムシのイラストに類似する。
ヒゲナガハマトビムシ(Trinorchestia trinitatis)_3d
撮影倍率:x2(実体顕微鏡)
特徴:第1咬脚の画像。
ヒゲナガハマトビムシ(Trinorchestia trinitatis)_3c
撮影倍率:x1(実体顕微鏡)
特徴:第2触角の拡大画像。
鞭部が柄部よりも長い。
ヒゲナガハマトビムシ(Trinorchestia trinitatis)_3b
撮影倍率:x40(生物顕微鏡)
特徴:第1触角の拡大画像。
ヒゲナガハマトビムシ(Trinorchestia trinitatis)_3a
採取:北海道石狩市(2016年9月)
撮影倍率:x0.67(実体顕微鏡)
体長:20.3mm
第1触覚:2.0mm
第2触覚:14.3mm 柄部6.4mm 鞭部7.9mm
特徴:第2触角の鞭部が柄部よりも長いことが特徴。
ホソハマトビムシ(Paciforchestia pyatakovi)も鞭部が柄部
よりも長いという特徴を持つが、この個体の第2触角は体長の
3/4程度であり、ホソハマトビムシの記載よりも明らかに長い。
複眼もホソハマトビムシの記載よりも大きく、
ヒゲナガハマトビムシの記載に一致する。
1mm
1mm
2mm
1mm
1mm
1mm
1mm
1mm
1mm
1mm
2mm
500μm
500μm
500μm
500μm
500μm
500μm
500μm
500μm
500μm
500μm
500μm
500μm
3mm
3mm
3mm
3mm
3mm
3mm
3mm
2mm
2mm
2mm
11a
10a
9a
8a
7a
6a
5a
4o
4n
4m
4l
4k
4j
4i
4h
4g
4f
4e
4d
4c
4b
4a
3k
3j
3i
3h
3g
3f
3e
3d
3c
3b
3a
-------------------------------------------------------------------------------------------------
参考文献:原色検索 日本海岸動物図鑑[II] 西村三郎 編著 保育社、1995年、p189-191.
日本産土壌動物 分類のための図解検索 【第二版】 青木淳一編著、東海大学出部、2015年、P1086,1089.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1a
ヒゲナガハマトビムシ(Trinorchestia trinitatis)
採取:北海道石狩市(2020年9月)
体長:8.4mm
特徴:2016年に石狩市で採取した個体よりも小さい。
Since 2005/9 Copyright 2023 Neko no Shippo
ヒゲナガハマトビムシ(Trinorchestia trinitatis)
採取:北海道石狩市(2020年9月)
体長:10.1mm
特徴:2016年に石狩市で採取した個体よりも小さく、
触角もやや短い。
2020年は個体数は多かったものの大型個体は見られなかった。
2mm
2mm
2a
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ここで記載する種は2017年の更新ではホソハマトビムシ(Paciforchestia pyatakovi)はとしていましたが、日本海岸動物図鑑II
だけでなく、日本産土壌動物も含めて分類を再検討したところ、ヒゲナガハマトビムシ(Trinorchestia trinitatis)として同定するのが
妥当だろう、という結論にいたりました。ホソハマトビムシと、ヒゲナガハマトビムシはどちらも第2触角の鞭部が柄部よりも長いことが
特徴ですが、ヒゲナガハマトビムシのほうが第2触角が長いです。また、ヒゲナガハマトビムシは眼が大きく、この特徴もこのページの
分類群に合致します。反対にホソハマトビムシは腹肢の内・外肢が未発達なのですが、このページの分類群の腹肢はそこそこ発達
しており、当てはまりませんでした。日本産土壌動物によれば、ヒゲナガハマトビムシ、Trinorchestia trinitatis (Derzhavin)は
体長18~25mm、眼が大きく半円形であること、第2触角の鞭状部が柄部よりも長いことが特徴。北海道から九州までの
砂浜に生息するとのことです。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2mm
1mm
2b
1c
1b