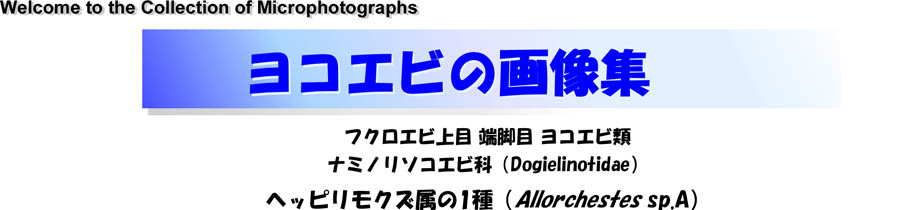ヘッピリモクズ属の1種(Allorchestes sp.)_9a
採取:新潟県出雲崎市(2016年4月)
撮影倍率:x40(生物顕微鏡)
体長:3.1mm
特徴:小型の個体。
幼体と思われる。
9a
8a
ヘッピリモクズ属の1種(Allorchestes sp.)_8a
採取:新潟県出雲崎市(2016年4月)
撮影倍率:x1(実体顕微鏡)
体長:5.9mm
第1触覚:1.4mm
第2触覚:2.0mm
特徴:第2咬脚が小さいので、雌、
あるいは幼体と思われる。
500μm
500μm
ヘッピリモクズ属の1種(Allorchestes sp.)_7a
採取:北海道紋別市(2016年9月)
撮影倍率:x3(実体顕微鏡)
体長:4.8mm 第1触覚:1.2mm 第2触覚:1.5mm
特徴:オホーツク海で採取した個体。
新潟で採取した個体に良く似ている。
第1咬脚の形状(前節が円形または角の丸い三角形)が
ヘッピリモクズ(Allorchestes carinata)に良く似ている。
ヘッピリモクズ属の正確な同定には尾節の形状(尾節板は先端部のみが
少し切れ込む)を観察する必要がある。
200μm
200μm
200μm
500μm
500μm
500μm
7f
7e
7d
7c
7b
ヘッピリモクズ属の1種(Allorchestes sp.)_6a
採取:新潟県出雲崎市(2016年4月)
撮影倍率:x1(実体顕微鏡)
体長:9.0mm
第1触覚:2.6mm
第2触覚:3.3mm
特徴:比較的大きな個体。
第2咬脚が大きいので雄と思われる。
ヘッピリモクズ属の1種(Allorchestes sp.)_6b
体長:9.0mm
特徴:拡大画像。
よく見ると眼がハート型。
1mm
2mm
7a
6b
6a
500μm
500μm
500μm
500μm
ヘッピリモクズ属の1種(Allorchestes sp.)_5a
採取:新潟県柏崎市(2016年4月)
撮影倍率:x1(実体顕微鏡)
体長:7.0mm
第1触覚:1.9mm
第2触覚:2.1mm
特徴:第1咬脚の形状(前節が円形または角の丸い三角形)が
ヘッピリモクズ(Allorchestes carinata)に良く似ている。
2019年に神奈川県湘南海岸、2020年に茨城県ひたちなか市で
ヘッピリモクズ属の1種(Allorchestes sp.)を採取したが、
神奈川・茨城県の個体群と、新潟の個体群は第1咬脚だけでなく、
触角の柄節の形状(緩い弧状)が酷似している。
ヘッピリモクズ属の1種(Allorchestes sp.)新潟・タイプ_4b
撮影倍率:x14実体顕微鏡)
特徴:触覚の拡大画像。
第2触覚の方が少し長い。
ヘッピリモクズ属の1種(Allorchestes sp.)_4a
採取:新潟県出雲崎市(2016年4月)
撮影倍率:x2(実体顕微鏡)
体長:8.0mm
第1触覚:2.2mm
第2触覚:2.6mm
特徴:第2触覚の鞭部が短い。
第2咬脚が大きいので雄と思われる。
ヘッピリモクズ属の1種(Allorchestes sp.)_3c
撮影倍率:x40(生物顕微鏡)
特徴:第2胸脚の拡大画像。
ヘッピリモクズ属の1種(Allorchestes sp.)_3b
撮影倍率:x40(生物顕微鏡)
特徴:第1胸脚の拡大画像。
ヘッピリモクズ属の1種(Allorchestes sp.)_3a
採取:新潟県出雲崎市(2016年4月)
撮影倍率:x2(実体顕微鏡)
体長:6.7mm
第1触覚:2.0mm
第2触覚:2.1mm
特徴:第1咬脚の形状(前節が円形または角の丸い三角形)が
ヘッピリモクズ(Allorchestes carinata)に良く似ている。
2019年に神奈川県湘南海岸、2020年に茨城県ひたちなか市で
ヘッピリモクズ属の1種(Allorchestes sp.)を採取したが、
神奈川・茨城県の個体群と、新潟の個体群は第1咬脚だけでなく、
触角の柄節の形状(緩い弧状)が酷似している。
ヘッピリモクズ属の1種(Allorchestes sp.)_2j
撮影倍率:x5(実体顕微鏡)
特徴:尾肢、尾節の拡大画像。
側面からでは内枝、外枝の構造が分かりにくい。
正面から観察する必要がある。
ヘッピリモクズ属の1種(Allorchestes sp.)_2i
撮影倍率:x40(生物顕微鏡)
特徴:第7咬脚の拡大画像。
ヘッピリモクズ属の1種(Allorchestes sp.)_2h
撮影倍率:x40(生物顕微鏡)
特徴:第6咬脚の拡大画像。
ヘッピリモクズ属の1種(Allorchestes sp.)_2g
撮影倍率:x40(生物顕微鏡)
特徴:第5咬脚の拡大画像。
ヘッピリモクズ属の1種(Allorchestes sp.)_2f
撮影倍率:x40(生物顕微鏡)
特徴:第4咬脚の拡大画像。
ヘッピリモクズ属の1種(Allorchestes sp.)_2e
撮影倍率:x40(生物顕微鏡)
特徴:第3咬脚の拡大画像。
ヘッピリモクズ属の1種(Allorchestes sp.)_2d
撮影倍率:x40(生物顕微鏡)
特徴:第2咬脚の拡大画像。
ヘッピリモクズ属の1種(Allorchestes sp.)_2c
撮影倍率:x40(生物顕微鏡)
特徴:第1咬脚の拡大画像。
ゲンコツのような形で特徴的。
ヘッピリモクズ属の1種(Allorchestes sp.)_2b
撮影倍率:x4(実体顕微鏡)
特徴:触覚の拡大画像。
第2触覚は第1触覚よりも長い。
ヘッピリモクズ属の1種(Allorchestes sp.)_2a
採取:新潟県出雲崎町(2016年4月)
撮影倍率:x2(実体顕微鏡)
体長:9.5mm
第1触覚:3.1mm
第2触覚:3.6mm
特徴:第1咬脚の形状(前節が円形または角の丸い三角形)が
ヘッピリモクズ(Allorchestes carinata)に良く似ている。
2019年に神奈川県湘南海岸、2020年に茨城県ひたちなか市で
ヘッピリモクズ属の1種(Allorchestes sp.)を採取したが、
神奈川・茨城県の個体群と、新潟の個体群は第1咬脚だけでなく、
触角の柄節の形状(緩い弧状)が酷似している。
ヘッピリモクズ属の1種(Allorchestes sp.)_1m
撮影倍率:x5(実体顕微鏡)
特徴:尾肢、尾節の拡大画像。
側面からでは内枝、外枝の構造が分かりにくい。
正面から観察する必要がある。
第2尾肢、第3尾肢に棘がある。
ヘッピリモクズ属の1種(Allorchestes sp.)_1l
撮影倍率:x4(実体顕微鏡)
特徴:第7咬脚の拡大画像。
ヘッピリモクズ属の1種(Allorchestes sp.)_1k
撮影倍率:x4(実体顕微鏡)
特徴:第6咬脚の拡大画像。
ヘッピリモクズ属の1種(Allorchestes sp.)_1j
撮影倍率:x5(実体顕微鏡)
特徴:第5咬脚の拡大画像。
ヘッピリモクズ属の1種(Allorchestes sp.)_1i
撮影倍率:x5(実体顕微鏡)
特徴:第4咬脚の拡大画像。
ヘッピリモクズ属の1種(Allorchestes sp.)_1h
撮影倍率:x5(実体顕微鏡)
特徴:第3咬脚の拡大画像。
ヘッピリモクズ属の1種(Allorchestes sp.)_1g
撮影倍率:x5(実体顕微鏡)
特徴:第2咬脚の拡大画像。
ヘッピリモクズ属の1種(Allorchestes sp.)_1f
撮影倍率:x40(生物顕微鏡)
特徴:第1咬脚の拡大画像。
ゲンコツのような形で特徴的。
ヘッピリモクズ属の1種(Allorchestes sp.)_1e
撮影倍率:x5(実体顕微鏡)
特徴:第2触覚の拡大画像。
柄部が長い。
鞭部は12節。
ヘッピリモクズ属の1種(Allorchestes sp.)_1d
撮影倍率:x5(実体顕微鏡)
特徴:第1触覚の拡大画像。
ヘッピリモクズ属の1種(Allorchestes sp.)_1c
撮影倍率:x3(実体顕微鏡)
特徴:拡大画像
底節板に焦点を合わせた。
ヘッピリモクズ属の1種(Allorchestes sp.)_1a
採取:新潟県柏崎市(2016年4月)
撮影倍率:x1(実体顕微鏡)
体長:9.5mm
第1触覚:2.9mm
第2触覚:3.7mm
特徴:第1咬脚の形状(前節が円形または角の丸い三角形)が
ヘッピリモクズ(Allorchestes carinata)に良く似ている。
2019年に神奈川県湘南海岸、2020年に茨城県ひたちなか市で
ヘッピリモクズ属の1種(Allorchestes sp.)を採取したが、
神奈川・茨城県の個体群と、新潟の個体群は第1咬脚だけでなく、
触角の柄節の形状(緩い弧状)が酷似している。
ヘッピリモクズ属の正確な同定には尾節の形状(尾節板は先端部のみが
少し切れ込む)を観察する必要があるが、
上記の類似点のため、新潟の個体群をヘッピリモクズ属の1種
(Allorchestes sp.)と同定することにした。
ヘッピリモクズ属の1種(Allorchestes sp.)_1b
撮影倍率:x2(実体顕微鏡)
特徴:拡大画像。
第2咬脚が大きいので雄と思われる。
500μm
500μm
500μm
500μm
500μm
500μm
500μm
500μm
500μm
500μm
500μm
500μm
500μm
500μm
500μm
500μm
500μm
500μm
500μm
500μm
500μm
500μm
1mm
2mm
1mm
1mm
1mm
1mm
1mm
2mm
5b
5a
4b
4a
3c
3b
3a
2j
2i
2h
2g
2f
2e
2d
2c
2b
2a
1m
1k
1l
1j
1i
1h
1g
1f
1e
1d
1c
1b
1a
500μm
500μm
500μm
500μm
5j
5i
5h
5g
5f
5e
5d
5c
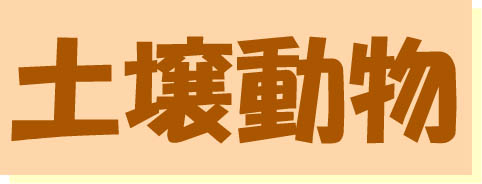
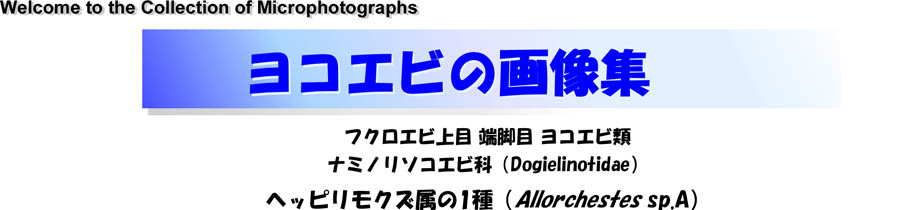
Since 2005/9 Copyright 2023 Neko no Shippo
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ここで記載する個体群はヘッピリモクズ属の1種(Allorchestes sp.)と思われます。ヘッピリモクズ(A. carinata)は体長40mm、
九州西岸と北海道から知られています。第3尾肢は単肢、先端に棘を欠きます。尾節板は先端部のみが少し切れ込みます
(日本海岸動物図鑑II)。1995年出版の日本海岸動物図鑑IIではヘッピリモクズ属はモクズヨコエビ科に含められていますが、
その後の研究によりナミノリソコエビ科に移されました。ここでは新潟県で採取したヘッピリモクズ属の1種を記載します。
尾節板を観察していませんが、第1咬脚の形などからヘッピリモクズ属と同定しました。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------